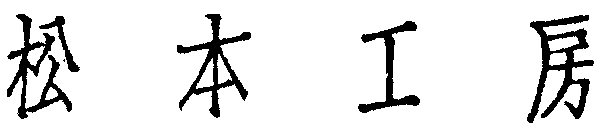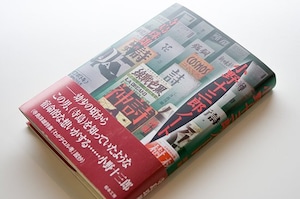小野十三郎ノート〈別冊〉
¥2,530
SOLD OUT
寺島珠雄 著
四六版/128×188mm/253頁
上製本/1997年
978-4-944055-31-9
巨大な詩人・小野十三郎。その最期までを見守り側近にいた著者による詳細な年譜解説など、在りし日と没後の記録集成。
ちいさなものをいとしんで
小野十三郎さんを悼む
10月8日午後、朝からの雨がやみそうになったころ、洋傘を外に置いて小野家の玄関に入ると、次男の浪速さんが振り向いて「いま、いまでした!」と私に叫んだ。
見通しの部屋の奥、小野十三郎さんのベッド際に浪速さんは立っていた。並んで毎週往診してくれる近所の前○医師も立っていた。
仰臥した小野さんの左側には三女の敏子さんが上って人工呼吸をつづけ、右側では四女の宏子さんがじっと手を握り、ともに泣きじゃくりつつ「おとうちゃん、おとうちゃん」と呼んでいた。
ついに、と私は小野さんを見た。
いままでならうなずくように動いた目が静止のままだった。そしてなぜか、小野さんの顔がすうっとひとまわり収縮したような気がして、もちろん錯覚にきまっているが、私はその錯覚から小野さんの最新詩集『冥王星で』の詩「ちいさなもの」を想起した。
わたしの好きな詩は
一節の終りが
みなちいさなものにしぼられている。
この3行で始まる詩は全部で20行、自作に登場させたちいさなものを作者小野さんが思い出して、それらへの親愛を述べている。
もっと肝心なちいさなものがありましたよね――無声で、私は小野さんに語りかけたが答えが返るわけはない。そんな仮想問答をやめて人の死に伴う実務の末端に加わる必要があった。そして11日未明の現在、机に戻って肝心なことの確認が出来たところである。
小野さんには『雑話集 千客万来』という著書があって、エッセー「縄文のゆめ」「まぼろしのふるさと」が収録されている。
二つのエッセーの要点を引用する。
――邪馬台がすでに一つの国家であるならば、大和にあろうと、北九州のどこかにあろうと、そんなことはどうでもいい……
――縄文の時代には、帝国も豪族もいなかった……
――国家ではない。自立する小さな「村」探しをわれわれはやろう……
いずれも1970年の執筆で、小野さんは自分の立論が「理論的に崩壊」することを認めている。つまり夢という自覚がある。他の文章で小野さんはその夢をユートピアともコンミューンとも呼んでいるが、東洋思想で言えば老子の説いた「小国寡民」や陶淵明の書いた「桃源」に通じる。
小野さんは青年期にアナキズムの詩人・理論家として立ったが、70年と言えば外的な運動から退いて既に歳月を経ている。それでもなお、あえて小さな村探しのわが夢を語るのは、思想の核心に無支配無権力の小社会理想郷を保っていることだった。おそるべき持続力。おびただしい作品群を生んだ土壌はこの持続力、加えて持続を可能とさせる柔軟性にあった。そういう稀少な人物をどう悼めばよいのか私は表現を思いつかない。
代わりに持続力の別な例をあげてみよう。
小野さんの『詩論』だ。これは戦中の1942~43年に雑誌発表したものが戦後に単行本化されたが主要な命題の一つに「リズムは批評であり生活である」というのがある。私は小野さんの古い手帳を預かって判読解明中だが、1936~37年使用の一冊に「生活のリズム、リズムを批評として感知する能力」という記入があった。雑誌発表開始に少なくも5年先行した発想が持続された実証である。
小野十三郎とはそういう人だった。
いや、まだ4日目でしかないのに、もう私は「人だった」と過去形で書いている。無意識の意識がさせた区別とでも言うか、それがなんともつらく申しわけなく思う。しかし小野さん、あなたは奥さんや大勢の友人のいる方へ出発したのだ。そちらでもちいさなものをいとしんで下さい。 (詩集・冥王星で 92年7月エンプティ刊▽雑話集・千客万来 72年5月秋津書店刊 評論集・詩論 47年8月 真善美社刊)